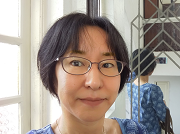|
Position |
Professor |
|
Degree |
M.Phil. (Anthropology)(London School of Economics and Political Science, University of London) |
|
Research Field |
Humanities & Social Sciences / Cultural anthropology and folklore |
|
External Link |
|
|
|
Graduating School 【 display / non-display 】
-
Osaka University Faculty of Literature Department of Japanese Studies Graduated
1990.4 - 1994.3
Graduate School 【 display / non-display 】
-
Osaka University Graduate School, Division of Human Science Doctor's Course Completed
1997.4 - 2003.3
-
Osaka University Graduate School, Division of Human Science Master's Course Completed
1995.4 - 1997.3
Studying abroad experiences 【 display / non-display 】
-
2000.4-2001.9
Goa University Visiting Student
-
1997.10-2000.6
London School of Economics and Political Science, University of London M.Phil. Course
Campus Career 【 display / non-display 】
-
KONAN UNIVERSITY International Exchange Center Konan International Exchange Center Director in General
2021.4
-
KONAN UNIVERSITY International Exchange Center Deputy Director
2018.4 - 2019.3
-
KONAN UNIVERSITY Faculty of Letters Faculty of Letters Department of Sociology Professor
2016.4
-
KONAN UNIVERSITY Faculty of Letters Faculty of Letters Department of Sociology Associate Professor
2014.4 - 2016.3
External Career 【 display / non-display 】
-
Nara University Faculty of Sociology
2009.4 - 2014.3
Country:Japan
-
Nara University Faculty of Sociology
2005.4 - 2009.3
Country:Japan
-
Osaka University Graduate school of Human Sciences
2004.5 - 2005.3
Country:Japan
-
Japan Society for the Promotion of Science
2003.4 - 2004.4
Country:Japan
Professional Memberships 【 display / non-display 】
-
Association for Asian Studies
2023.2
Papers 【 display / non-display 】
-
インドの大学における「自己語りの社会学」の試みとその意義: Hanv Konn?: Researching the Selfの公開・出版の経緯から考える
松川恭子
『甲南大學紀要.文学編』 173 123 - 130 2023.3
Authorship:Lead author
-
インドの都市における演劇を通じた故郷の想像/創造――ティアトル劇のボンベイでの発展と「ゴア人の物語」の還流
松川恭子
『甲南大學紀要.文学編』 171 157 - 171 2021.3
Single Work
Books and Other Publications 【 display / non-display 】
-
Transnational Generations in the Arab Gulf States and Beyond Reviewed International journal
Kyoko Matsukawa, Akiko Watanabe and Zahra R. Babar (eds.)( Role: Joint editor , "Introduction"; Chapter 7 "The Return Experience and the Perpetual In-betweenness of Gulf-born Non-resident Indians: Analysis of Cases in Kuwait")
Springer 2023.12 ( ISBN:978-981-99-5182-6 )
-
世界のクリスマス百科事典
樺山紘一・中牧弘允(編)( Role: Contributor , インド共和国)
丸善出版 2023.11 ( ISBN:978-4-621-30847-9 )
-
南アジアの新しい波 下―環流する南アジアの人と文化 Reviewed
三尾 稔(編)( Role: Contributor , ローカル視点からみるインド映画の新潮流 ――コーンカニー語映画を事例に)
昭和堂 2022.3 ( ISBN:9784812221198 )
-
粟屋利恵・太田信宏・水野善文(編)( Role: Contributor , コーンカニー文学―ポルトガル支配の影響)
東京外国語大学拠点南アジア研究センター 2021.3 ( ISBN:978-4-907877-23-1 )
Review Papers (Misc) 【 display / non-display 】
-
新旧征服地の違いからゴアの独自性を見る
松川恭子
『月刊みんぱく』5月号 47 ( 5 ) 6 - 7 2023.5
Authorship:Lead author
-
書評 Tejaswini Ganti, Producing Bollywood : Inside the Contemporary Hindi Film Industry
松川 恭子
『アジア経済』 55 ( 4 ) 112 - 116 2014.12
Presentations 【 display / non-display 】
-
インドの大学における自己語りを活用した教育実践の展開:Hanv Konn?(私は誰?)の問いから考える
松川恭子
日本南アジア学会第37回全国大会 2024.9
-
Migration and Cultural Gyres of Indian Ocean Performing Arts: The Case of Goans and Their Popular Theatre, Tiatr (Panel: Unruly edges of Indian Ocean arts: Objects and ideas in circulation and transformation)
Kyoko Matsukawa
Arts of Indian Ocean Conference (University of Toronto Missisauga) 2024.5
Country:Canada
-
The Perpetuated “In-betweenness” Experienced by Gulf-born NRIs: Analysis of Cases in Kuwait
Kyoko Matsukawa
The 5th Philippine Studies Conference in Japan (PSCJ 2022 in Tokyo) (The University of Tokyo (Komaba Campus)) 2022.11 Annual Phillipine Studies Forum in Japan
-
Return Experience and the Perpetuated “In-betweenness” of Gulf-born NRIs: Analysis of Cases in Kuwait
Kyoko Matsukawa
An International Workshop on Migration and Citizenship Quests: Transnational Generations in the Gulf and Beyond (Kyoto University) 2022.11 KAKEN project Long-Time Temporariness and the Quest for Citizenship: A Study of Second-Generation Asian Gulf Migrants
-
インドの大学において自己を語ること―Hanv Konn(私は誰)の試みから考える―
松川恭子
日本南アジア学会第35回全国大会 (帝京大学(八王子キャンパス)) 2022.9 日本南アジア学会
Grant-in-Aid for Scientific Research 【 display / non-display 】
-
インド・ゴアにおける自己語り/複数メディアを活用した教育と発信の人類学的実践研究
2020.4 - 2024.3
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
松川恭子
本研究は、インド・ゴア大学社会学科で、故Alito Siqueiraが修士課程卒業生たちに推奨した自己語りを通じた教育/複数メディアによる発信に申請者が関わる人類学的実践研究を行う。この作業により、「自己語り」という営為をめぐり現われるインド社会の文化的諸問題、「自己語り」のエンパワーメントの契機としての力、複数メディアでの発信による共感の拡がり・ネットワーク形成の可能性を明らかにすることをめざす。 -
インドにおける新しいメディア状況と芸能のグローバル化:文化の環流の人類学的研究
2014.4 - 2018.3
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research(B)
本研究は、芸能に焦点を当てることで(1)インド社会の2000年以降の構造・価値観の変化を捉え、(2)西洋発の文化が世界中に拡大するという従来のグローバリゼーション・モデルとは異なる、文化の環流現象のモデル化を目指すものである。環流現象とは、国境を越える過程で変化し、様々な地域への拡大と自社会への回帰を見せる、近年のグローバルなインド文化の動態である。本研究課題では、演劇、舞踊、音楽という芸能が衛星放送、携帯電話、インターネット等からなる新しいメディア状況と結びついて世界各地に広がるとともに、インドに回帰することで生じるインド社会への影響を明らかにする。
-
インドのナショナルな大衆文化の系譜と演劇にみる地域的想像力の展開―ゴアの場合
2009.4 - 2013.3
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists(B)
本研究が目指すのは、西部インド・ゴア社会の大衆演劇ティアトルの系譜を歴史的資料と現在の実践者に対する文化人類学的聞き取り調査によって明らかにし、19世紀~現在のインドにおけるナショナルな大衆文化の系譜のなかに位置づけることである。従来の研究で明らかにされてきたように、大衆文化の想像力が地方、都市を経てネーション意識を生み出す一方で、そのナショナルな大衆文化が、地域アイデンティティの再編成に環流し、独自の発展を遂げていった「地域的想像力」の編成過程に着目する。本研究でキーワードとなる「想像力」の語については、C・W・ミルズ(『社会学的想像力』)やA・アパデュライ(『さまよえる近代』)の用法を発展させ、自己を取り巻く世界を理解すること、その世界に関する知を生み出すために必要な力、と定義し、地域社会がグローバル化された公共圏・市民社会にアクセスする可能性についてより能動的に描き出すことを試みる。地域社会に固有の歴史・社会関係と結びついた知識・情報の伝達と共有のメカニズムに歴史的な状況が重なって、地域社会の想像力が発現してきたことに留意する。本研究が最終的に目指すのは、人々が大衆文化を単に消費するだけでなく、その中で独自の想像力を働かせてグローバル化した世界における自分のポジションを理解し、声を発していくことのできる可能性について考えていくことである。
-
Anthropological Study of Productivity of Borders and Transnationality
2005.4 - 2009.3
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research(B)
-
インド・ゴア社会の大衆演劇「ティアトル」をめぐる実践と共同性の文化人類学的研究
2005.4 - 2008.3
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists(B)
ゴアの大衆劇「ティアトル」に関わる人々の実践を通じ、ゴア社会におけるカトリック教徒の共同性の現れを明らかにした。ティアトルは、毎週のように劇場で上演されるミュージカル仕立てのゴアの現地語(コーンカニー語)劇で、イタリア・オペラに着想を得て19世紀末、ムンバイ(旧ボンベイ)のゴア人によって始められた。現在は、多数のプロ劇団が存在するのみならず、アマチュア劇団の活動も盛んであり、年に数回ティアトル・コンペが行われている。ティアトルの実践者、受容者のほとんどがゴア人カトリックである理由を明らかにするため、現地調査を実施した。ポルトガル植民地時代の19世紀以来、ゴア人、特にカトリックの人々は、雇用機会を求めてゴアの外部(ムンバイやデリー等のインド大都市・ヨーロッパ・アメリカ・中東湾岸諸国)へ出稼ぎ・移住を行っている。このようなディアスポラの人々も含め、ティアトルをめぐる共同性の発現を明らかにすることが、本研究の第一の目的だった。